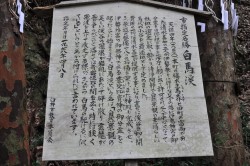|
 |
| こちらが正面。真っ暗な中で田んぼに入って撮りました。 | 製作者の梅津さん自身が見学に来た人たちに説明をしている。子どもたちが喜ぶのが一番うれしいとか。 |
神戸まで2時間ごとに休憩を取りながら約7時間で走る。新幹線の時も思ったけれどトンネルの多いこと。時には1キロを超えるトンネルが5つも続いている箇所もある。書写山という看板を見たところでは連続7つというのさえあった。ほとんど山の中を走るが、今年は12月を過ぎても紅葉が残っている。
福山SAから次の三木SAまでを1時間10分くらいですと言っていたのに、ジャスト2時間かかる。すいません。引き算を間違えました。3歳児の計算能力でした、と添乗員は言うが、3歳児が聞いたら腹を立てそうだ。この添乗員は憎めないキャラの持ち主だった。予定の時間が来ると帽子を被って身構えていたお年寄りが、SAに着くと女性たちよりも早くトイレに急ぐ。年を取るというのは大変だ。
中国道から神戸へ行く入り口を見落とし、何十メートルか進んでしまう。そのままバックしていく。みんなあっけに取られたが、しまいには笑い出してしまう。運転手くん、冷や汗者だっただろう。少し行くと看板が出ていた。「高速道路では逆走しないで下さい!」。今度は出口を間違える。料金所の方が再入場させてくれる。その時のやり取り。
どこからですか? - 九州です - 分かりました。
こういうのを【思いやり】または【絆】という。