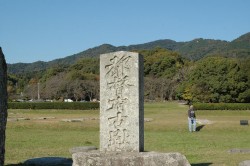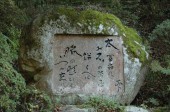|
|||
 |
 |
 |
 |
ふぐでは下関が全国的に知られているが、大分県では下関より臼杵である。12年ほど前、忘年会で門司港のホテルに泊まり、そこから下関のかの有名な「春帆楼」でふぐを食べるという経験をしたことがあるが、新鮮さが命のふぐ刺しは造り置きなのかラップに包まれ、刺し身同士が粘っこくくっついているという悲惨な目に遭った。名前だけで行くもんじゃないという貴重な体験をさせてもらった。
ここはそんなことは絶対に起きない。もちろん下ごしらえはしているのだろうが、こちらの進み具合に合わせて次の料理を運ぶという、当然の心遣いをしてくれているのでほんとに美味しい。私はグルメレポータではないので、味について上手く表現できない。写真も美味しく撮れているか自信はないが、ぜひ写真を拡大して鑑賞してください。ひれ酒(別注文)を入れて10品。出された順番に掲載します。
⑥「白子に寿司」-口の中でとろける白子は絶品。
⑦「水炊き」-この辺になるとだんだんとペースが落ちてくる。
⑧「唐揚げ」-おそらくこの順番はお店の失敗だと思う。
⑨「吸い物」-みんなは中に入っているふぐの口の部分(おちょぼ)が美味いというが、姿を見るだけでもうだめだ。
⑩「雑炊」-腹がいっぱいだと言いながら、どうして2杯も食べたのか!これが食べたくてここまで来ているのかもしれない。