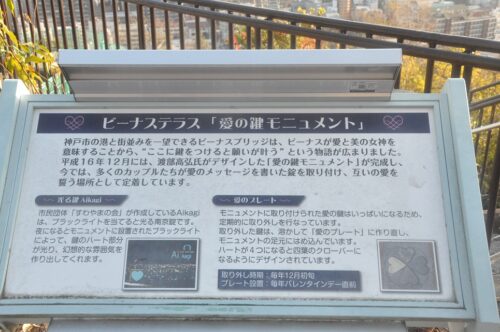この天龍寺は(あとでも書くが)
足利尊氏が御醍醐天皇を弔うために建てたお寺である
というと凄くいい話のように聞こえるが、要は「祟り」を恐れたからである
臨済宗の大本山で、臨済宗といえば習いましたね
「五山制度」です
その臨済宗の五山制度の第一位がこの天龍寺である
ここまでは覚えていましたが、この後はネット学習
別格 ; 南禅寺
一位 ; 天龍寺
二位 ; 相国寺
三位 ; 建仁寺
四位 ; 東福寺
五位 ; 万寿寺
 |
 |
さあ、第一位であり、世界遺産でもある天龍寺の中へ入ってみましょう
総門の左横に巨大な石碑が建っているので見ておきましょう
まあ嫌でも目には入りますけど
それに比べて、総門自体は天龍寺の寺格からすると、
拍子抜けするくらい、小ぶりである