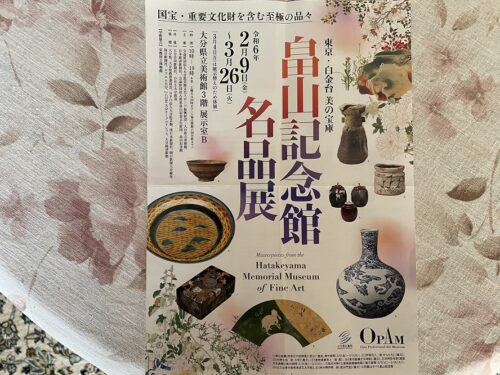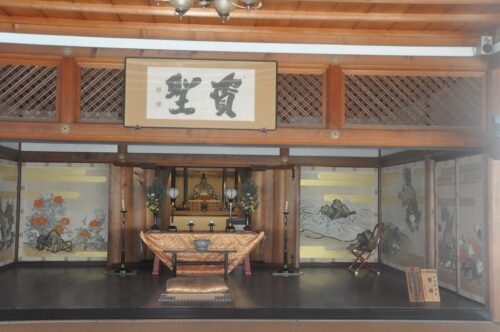毎度毎度、米山公園で申し訳ありません
いかに私の行動半径が狭いかが一目瞭然です
この公園にも何本かの桜が植えられています
ほとんどの桜がやっと蕾から花を咲かせ始めるようになってきました
そんな中、1本の「枝垂桜」が見事な姿で花を咲かせています
27日・29日・31日・1日と連続で写真を撮りました
最後の写真には地面に花びらが落ちています
 |
 |
 |
 |
何か病気をしたわけでもないのですが、あちこちに痛みが出て、
満開の桜を求めてどこかへ行こうという気分ではありません
幸い、毎日この公園で歩くのだけはできているので、
この桜が蕾を作り、花が咲いて、満開になり、散っていくのを楽しみましょう