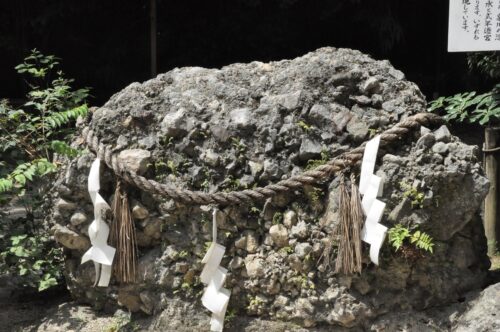朝から雨音が聞こえています
九州北部も梅雨に入りましたと先ほど宣言がありました
庭の花たちも心なしか元気になったようです
 |
 |
 |
 |
それでは下賀茂神社に戻りましょう
楼門をくぐると、
ふつう少し広い広場があって、その正面に本殿がある
太宰府などでおなじみの配置である
ところが、ここでは正面の、そして、広場の中央に重厚な建物が鎮座している
「舞殿」である
 |
文字通り「鎮座」という言葉にふさわしい貫禄がある
なんでこんなところ(境内の中央)にと思ったら
京都三大祭りの一つ、「葵祭」の時に、
ここで天皇の勅使が御祭文(ごさいもん)を奉上し、
東遊(あずまあそび)の舞が奉納される場所、と看板にある
重厚で、貫禄があって、鎮座するあなたに「なんで」なんて失礼なこと 申し訳ありません
重要な役割を担っていたんですね