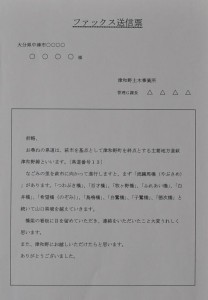 |
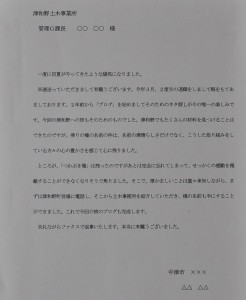 |
津和野は「つわぶきの生い茂る野」をその名のルーツに持つといわれている。遠い昔、この地に住み着いた人々は、群生する「つわぶき」の可憐な花に目をとどめ、自分たちの住む野を「つわぶきの野」から「つわの」と呼ぶようになったというのである。そのことばの響きの中にはこの地に対する彼らの誇りとツワブキの葉の艶やかさに通じる美意識とかすかな自慢めいたものが感じられて好ましい。
そうした美意識は今も残っているようだ。帰りは県道13号を通る。別名「つわぶき街道」と呼ばれている。運転しながら気がついたことがある。それは橋とはとうてい言えないほどの小さな橋に名前がついており、それぞれに大きな標識が立てられているのである。それも普通使われる地名に由来するものではない。「つわぶき橋」など津和野に由来することばを冠するところに美意識と誇りがにじみ出ていて、「感じいいね~!」とこちらの気持ちも明るくなってきた。ところが、帰り着いたら覚えたはずの名前をほとんど忘れてしまっていた。
なんとかこの感動を伝えたくて、厚かましくも津和野町の観光課に電話して教えを請う。応対に出た若い職員の方が調べてくれて、県道なのでと「県・津和野土木事業所」を紹介してくれた。土木事業所では管理課長さんが丁寧にファックスで地図まで送ってくれ、おまけに「橋梁の看板に目を留めていただき、連絡をいただいたことを大変うれしく思います」とまで言ってくれた。
私の厚かましいお願いを受け止めてくれて、丁寧に対応してくれた観光課の職員さんと土木事業所の管理課長さんに、改めて感謝の意を表したいと思う。これだから人とのふれあいは止められない!

つわぶき橋っていいなまえですねぇ。
最近は趣のある昔の名前を、味も素っ気もない記号のような名前に変更することが多く残念に思っていました。
以前から気になっていた津和野の名前の由来も、〈つわぶきの野〉だと初めて知りました。
北海道も大きな蕗科の植物が物凄くたくさんあって驚きましたが、勝手に思うに、
津和野のつわぶきは、群生とまではゆかない、やさしい感じに思えています。
写真の二つあるファックスがどうにも気になり拡大してしてみました。
流鏑馬橋に続き、村人達のやさしさが伝わるような名前ですね。
先輩、お久しぶりです!
退職後の健筆振りに圧倒されながら、ずーと楽しませて貰ってます!
柳川にも健軍にも、そして「津和野!」山陰の最西端、山陰に居ながら
近くて、遠い! 小生も我が女房殿といつかは訪れたいと・・・・・・!
その時は、先輩のこの「津和野紀行」を携えて行こうと、思っとります!
先輩の充実した退職後の行動力を見習いたいヒロより
橋の名前のブログができた感謝の気持ちで土木事業所の課長さんにその旨を書いたFAXを送ってしまいました。そのことも番外編としてそのまま使おうかなと思っています。/今わたしも庭木を1本ばっさりと切ってきました。水路の横に、鳥が置いていったのか大きくなりました。切っても切っても次の年には同じくらいの背丈の伸びてしまいます。あと何年梯子に登れるだろうかと心配になり、倉庫の奥からチェンソーを引っ張り出して、「ばっさり」と切ってしまいました。/「そっと頬を包みながら」を読みました。「翻弄」ということばと「理不尽」ということばが胸に突き刺さります。であるだけに「掌でそっと頬を包」む動作が胸に沁みます。
どうしたのかなと思い始めた頃に、絶妙のタイミングでコメントが届きました。忘れられたのかと心配しました。可笑しいのは「あっちゃん」とぴったり同じ時に二人のコメントが届いたことです。ここ2・3日ブログが書けませんでした。ようやくなおったのでそのことから書きます。あと2回で津和野も終わりです。