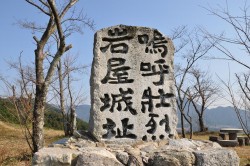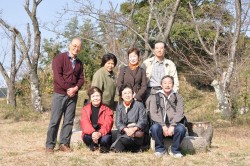|
 |
 |
| 広い道路から斜めに | 田んぼに入って正面から | 斜め後ろから |
一緒に働いて、楽しかった思い出のある方と久しぶりにばったり出会った。自然にワクワクしてきて今日は得をしたような気になった。
夜のウォーキングの途中、今日も始まっていなかったね、というのが日課になっていた。昨年は11月の20日過ぎには点灯していた。昼間、車で前をわざわざ通った時、家族総出で準備していたよ、と連れ合い。もう何年も毎年素晴らしいイルミネーションを見せてくれていた家がある。昨年は登山の会の人たちを反省会の後、みんなを誘って見に行ったほどである。他の家がバージョンアップして早くも始まっていたので、他人事ながら心配になっていた。
昨夜(4日)、いつものようにウォーキングに出ると、遠くの方に今までにない灯りが見える。ワンダーランドじゃないのというが、位置が違うよと答える。クロネコヤマトの近くにやってくると、向かいの家の先にものすごい灯りが見えた。「ものすごい」と書いたが大げさではない。「ヒエー!」となんとも変な声が出てしまった。どんなに言葉で説明してもしたりない。昨年もすごかったのに、今年はまた一段とバージョンアップである。
三脚使用 ストロボなし 撮影モード(A) 絞り(F8) ISO(800)