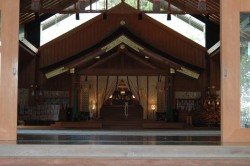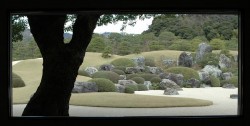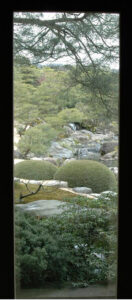|
 |
 |
 |
小倉発9:55 ひかり552号。姫路には11:50に着くので、約2時間本を読んで過す。姫路駅に着いたとたん、なんの前触れもなく右足のふくらはぎが痛み出す。その痛みが半端ではない。なんとか駅からお城に向かって歩き出すのだがますます痛くなる。とうとう歩けなくなり、連れの二人には先にお城に向かってもらう。
私は病院を探す。全く知らない土地で、おまけに今日は日曜日。やっと交番を見つけて病院を聞くと、近くに「姫路医療センター」があることを教えてくれた。もちろんそれ以上は歩けないのでタクシーを何とか見つけるが、そのタクシーがセンターまでのわずかな距離をたどりつけない。日曜日、おまけに12日から大修理が始まって、天守閣は5年後でないと見ることができないという。旅行会社は「見納め姫路城」というキャッチフレーズでツアーを組む。そして、マスコミはたくさんの人が集まった様子を繰り返し放映する。今行かなければ乗り遅れるぞ!と言わんばかりである。おかげでお城の周りは人と車で埋め尽くされた状態である。
なんとかたどりついて救急の担当医に診てもらう。レントゲンまで撮った結果は、軽い肉離れでしょうということだった。面白いものでシップを貼り、痛み止めを飲んで、医者に診てもらったことが効いたのかなんとか歩けるようになる。しかし、待っている間にいろんな人生ドラマを見る。病院の待合室というのは人生の縮図である。ところが、今回保険証を持っていなかったので実費を取られる。保険制度の有り難味が良くわかった。
連れと巡り会えたのが15:30過ぎ。お城の横にあった美術館を訪れたあとは、ただひたすら彼らの出てくるのを待つだけ。散々な姫路城ではある。
前回(3月28日)来た時に見た西ノ丸はすでに化粧が終わっていた。青空の中に白い壁が輝いて、5年後は必ず天守閣を見たいものだと思った。それまで元気でいなければ・・・・。