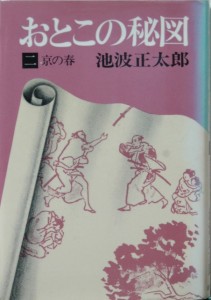 |
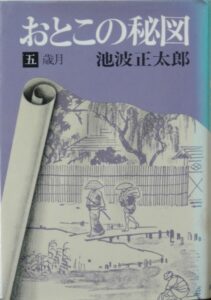 |
池波正太郎に女性を描かしたら、彼の右に出る作家はいないのではないかと思っている。この小説でも、二人の魅力的な女性が登場する。ひとりは京都で出会う「お梶」。そして、もうひとりは、江戸で妻となる「勢以」。そうか、司馬遼太郎の小説は、いくつかの例外を除いて、そう繰り返し読もうという気になれない理由は、案外ここにあったのかもしれない。彼の小説には女性が、それも魅力的な、生々しく生きている女はとんと出てこない。
「お梶」。明日、京都を密かに旅立とうという日、運命の女(やはりここは女性ではしっくりこない)、お梶と出会う。三人の浪人に難癖をつけられたお梶を権十郎が助ける。お礼にお茶など、という言葉にことわる理由もなく、お梶の営む茶屋「東林」に導かれる。
「女という生きものが、化粧もなしに、かほどまでに美しく見えたことは、いまもってない・・・・」(202p)というお梶との出会いと狂おしいほどの逢瀬。この場面、つまり、201pから241pまで何度繰り返しくりかえし読み返したかしれない。しかし、お梶は、権十郎はいずれは江戸に帰ることになると知っており、知っているからこそ「権十郎をさそったので」ある。「山口さま。同じ夢は、二度、見るものではないと申しまする」とささやくお梶の声がほんとに聞こえてきそうである。
「勢以」。江戸に帰り、徳山家を継いだ権十郎が妻として迎えた女性(今度は女ではしっくりこない)。お梶とは全く対照的な、女としての魅力を欠いた妻。その勢以に振り回される権十郎。「なりませぬ」であり「何をなされます」であり、「そのようなことを、あそばしてはなりませぬ」である。なんどもふきだしてしまう。そして、同情する。その勢以が、最後のさいごになって、ある意味、お梶にも負けない魅力的な女に変身する。昔、初めてこの本を読んだ時には、お梶の方にしか目がいかなかったが、、ようやくそれが分かる年になったのかなと思う。
もうひとつ、題名になっているおとこの「秘図」が重要な狂言回しになっている。そのことについても書きたかったが、「秘図」である以上、おおっぴらにはできない。池波正太郎の得意のせりふではないが、「すべてをあかしては、味気ない、あじけない」である。
